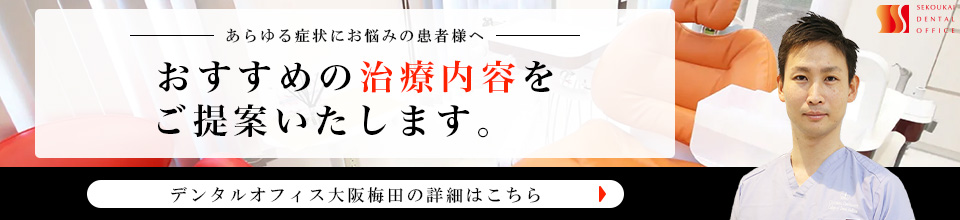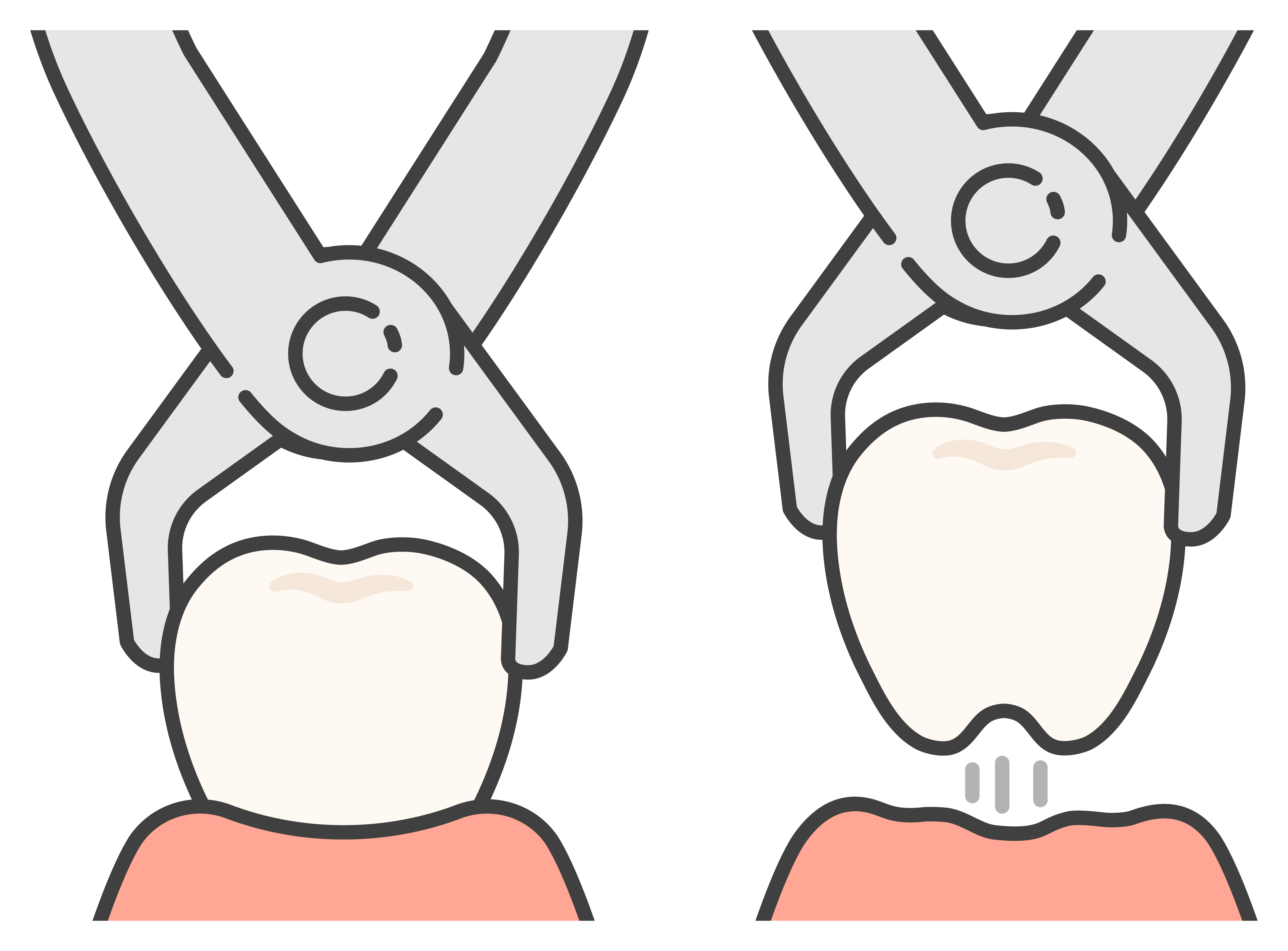梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」
〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画
親知らずはそのままでもよい?放置のリスクと抜歯が勧められるケース

「親知らずが生えてきたけど、放置したらどうなるの?」と不安を感じていませんか?
親知らずは、横向きに生えてきたり、歯茎に埋没していたりと、人によって生え方はさまざまです。
下手に放置すると、深刻な口内のトラブルにつながることもあります。
本記事では、親知らずを放置することで生じるリスクと、主な治療内容を解説します。
親知らずに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください
目次
親知らずとは?
親知らずは、永久歯の中で最後に発達する歯です。
上顎と下顎の左右、口内の一番奥に生える4本を示します。
生えてくる年齢は10代後半から20代に多く、「大人になって、親元を離れた頃に生えてくる歯」という理由から、親知らずとよばれています。
横向きに生えたり、歯肉に埋没していたり、そもそも親知らずが無かったりと、生え方は人によってさまざまです。
歯茎から出ている親知らずは、口内の一番奥にあるために歯磨きが難しく、虫歯になりやすいのが特徴です。
親知らずを放置すると、虫歯や歯周病になるだけでなく、ほかの歯に害を及ぼすおそれもあるので、早めに抜歯することをおすすめします。
親知らずを放置することで生じるリスク
放置した親知らずは、さまざまなトラブルを引き起こします。
この項では、親知らずを放置した際によく起こる、口内のリスクを紹介します。
虫歯・歯周病になりやすくなる
前述したとおり、不規則に生えた親知らずは、歯磨きが難しく虫歯になりやすいのが特徴です。
親知らずによって生じた隙間には汚れが溜まりやすく、普段の歯磨きや、うがいだけできれいにするのは困難です。
残った汚れは、親知らずを虫歯にするだけに留まらず、隣接する歯にも虫歯や歯周病といった疾患を引き起こします。
歯周病は、口内に残った汚れが原因で引き起こされる歯茎の炎症疾患です。
主な症状として、歯肉の腫れや痛み、膿の発生があげられます。
また、歯周病は重症化すると、炎症が顎や首にまで広がり、水が飲めないほどの痛みを発する可能性もあります。
日常生活に支障がでる
親知らずは、ほかの歯とぶつかるように生えてくると、歯全体の噛み合わせを悪くし、日常生活に支障がでるようなトラブルに発展することがあります。
なぜ、噛み合わせが日常生活に支障をきたすのかいうと、口の開閉時に無駄な負荷がかかり、血行が悪くなるからです。
血の巡りが悪くなると、顎周りの痛みや肩こり、頭痛といった症状を引き起こします。
また、悪くなった噛み合わせを放置した場合、口を開ける際に音が鳴ったり、痛みが生じたりする顎関節症(がくかんせつしょう)を発症するおそれもあります。
命に関わる症状ではありませんが、重症化した場合には別途の治療が必要です。
ほかの健康な歯に悪影響をあたえる
親知らずが隣の歯を圧迫するように生えてくると、隣接する歯の根っこが浸食され、溶けてしまうケースも見受けられます。
これは「歯根吸収(しこんきゅうしゅう)」とよばれる症状です。
根っこが溶けた歯は、歯を支える力が弱くなり、抜け落ちる危険性が高まります。
歯が抜けると、審美性に悪影響を及ぼすだけでなく、歯全体の寿命を縮めるので、早めの治療が必要です。
親知らずを抜いたほうがよいケース
一般的に、以下のケースは親知らずを抜くほうがよいと考えられています。
ケース①痛みや腫れが生じている
痛みや腫れが生じている場合は、歯科医院をできるだけ早く受診しましょう。
大きな虫歯になっていたり、歯肉が炎症を起こしていたりする可能性があるためです。
トラブルの例として、親知らずの周りの歯肉が腫れて痛む「智歯周囲炎」があげられます。
おもな原因は、汚れが溜まって細菌が増殖するためで、放っておくと症状は徐々に悪化します。
顔が腫れたり、熱が出たり、顎の骨が溶けたりする恐れもあります。
炎症を起こした親知らずは、同じ問題を繰り返すケースが多いため、抜歯するほうがよいと考えられています。
ただし、炎症を起こしている期間は抜歯を行えません。
まずは、痛みや腫れの治療が必要です。
ケース②斜めに生えている
親知らずが、斜めに生えているケース、あるいは横に生えているケースも、抜歯の必要性が高いといえます。
ひとつ前の歯(第二大臼歯)を押して、歯並びを悪化させる恐れがあるためです。
押された第二大臼歯は、さらにひとつ前の歯(第一大臼歯)を押します。
このような経緯で歯並びが乱れると考えられています。
具体的な影響はケースで異なりますが、抜歯により親知らずの影響を取り除けます。
また、斜めに生えた親知らず、横に生えた親知らずは、智歯周囲炎の原因にもなりえます。
第二大臼歯との間に、大きな隙間が生じるためです。
歯磨きを丁寧にしても、汚れを取り除けないため、細菌が繁殖しやすくなります。
これらのリスクが考えられるため、抜歯の必要性が高いと考えられているのです。
ケース③顎の骨の内部に嚢胞ができている
顎の骨や歯肉に埋まっている親知らずの周囲に、含歯性嚢胞と呼ばれる袋状の構造物ができる場合があります。
強い症状を引き起こすことはほとんどありませんが、放っておくと大きくなり顎の骨を溶かしてしまいます。
したがって、親知らずを抜歯してから嚢胞を摘出するケースが一般的です。
ただし、目立った症状が現れないため、本人も嚢胞の存在に気づいていないことが少なくありません。
他の検査で偶然発見されることが多いと考えられています。
トラブルを避けるため、定期的に検診を受けることが大切といえるでしょう。
ケース④噛み合わせが悪くなっている
親知らずの本数は、左側上下、右側上下の4本です。
しかし実際は、いずれかの歯が生えないこともあります。
片側の上だけ、あるいは下だけだと、噛み合う歯がないため本来の役割を果たせません。
それだけでなく、片側の歯が伸びて噛み合わせが悪くなったり、歯茎に当たってしまったりする場合があります。
顎関節へ負担をかける恐れもあるため注意が必要です。
放置してもメリットはないため、噛み合う歯がない場合も抜歯を検討します。
ケース⑤歯の矯正を予定している
矯正治療の一環で、親知らずを抜くこともあります。
抜歯を検討するおもなケースは次のとおりです。
【抜歯を検討するケース】
- 親知らずが歯並びに悪影響を与えている
- 歯を移動させるスペースが不足している
- 今後、歯並びに影響を与える可能性がある
たとえば、親知らずが横に生えていて、前の歯を押している場合は抜歯を検討するでしょう。
矯正治療の妨げになったり、後戻りの原因になったりするためです。
歯を移動させるスペースを確保したい場合も抜歯を検討します。
親知らずがあると、利用できるスペースが限られてしまうためです。
ただし、具体的な考え方は歯科医師で異なります。
矯正治療を受ける前に、抜歯の要否を確認しておくことが大切です。
親知らずが炎症を起こしている際の症状
ここからは、親知らずの周囲にある歯肉が炎症(智歯周囲炎)を起こした際に現れる症状を解説します。
発熱する
親知らずが炎症を起こしても、目立った症状は現れません。
基本的には、歯茎が赤く腫れる、硬いものを噛むと痛む程度です。
しかし、智歯周囲炎が進行すると、睡眠不足や疲労などをきっかけに、リンパ節が腫れて40度近い高熱が出ることがあります。
倦怠感や食欲不振、脈拍増加、呼吸数増多などの症状を伴うケースがある点もポイントです。
以上からわかるとおり、親知らずの炎症で引き起こされる症状は口腔内だけにとどまりません。
ケースによっては、全身に症状が現れることを理解しておく必要があります。
腫れが生じる
親知らずが炎症を起こすと、早い段階から歯肉が赤く腫れます。
また、歯茎を押すと痛い、歯茎がぶよぶよになるなどの症状が現れることもあります。
歯茎がぶよぶよになる理由は、膿が溜まるためです。
この影響で、歯肉ポケットから膿がしみだしてくることもあります。
ケースにより腫れ方が大きく異なる点もポイントです。
軽く腫れる程度のこともあれば、隣の歯まで腫れが広がること、第三者が見てわかるほど大きく腫れることもあります。
腫れが軽くても軽視せず、治療を受けることが大切です。
痛みを感じる
炎症にともない、痛みを感じることもあります。
腫れと同じく、痛みの程度はさまざまです。
歯茎を押すと痛い、硬いものを噛むと痛い程度のこともあれば、強い痛みを持続的に感じることやものを飲み込むときに強い痛みを感じることもあります。
基本的には、炎症が急性化すると症状がひどくなるといえるでしょう。
痛みが気になる場合は、歯科医院で相談すると症状を緩和する薬を処方してくれます。
口が開けにくくなる
炎症の影響で、腫れと痛みが強くなり、口を開けにくくなることもあります。
炎症が急性化したときに現れやすい症状で、第三者から見ても、顔の腫れがわかるケースが多いでしょう。
口を開けにくくなると、話すことや食事をとることが難しくなり、日常生活に悪影響が及ぶため注意が必要です。
腫れの範囲が広がると、抗菌薬の飲み薬では対処できないことがあります。
点滴が必要になるケースもあるため、医療機関を早めに受診することが大切です。
物が飲み込みづらくなる
炎症の範囲が広がると、口底や頸部なども腫れてしまうため、ものを飲み込むことも難しくなります。
強い痛みで、食事を満足にとれないことや水が飲めない場合もあります。
栄養失調や脱水症のリスクが高まるため十分な注意が必要です。
ケースによっては、入院治療が必要になることも考えられます。
単なる親知らずの炎症と考えず、適切に対処することが重要です。
親知らずの治療方法
親知らずの主な治療法は抜歯です。
抜歯後は、化膿している組織を取り除き、洗浄してから縫合します。
親知らずが埋まっている場合には、歯茎を切開してから歯を摘出し、縫合します。
とはいえ、すべての親知らずを抜く必要はありません。
虫歯になっていないか、ほかの歯に悪影響を及ぼしていないかなど、さまざまな条件をもとに判断することになります。
親知らずが生えてきた際には、歯科医師と相談したうえで、治療方針を決めましょう。
手順①抗生物質で炎症を抑える
炎症のおもな原因は、斜めや横に生えている親知らずの周辺に汚れが溜まり細菌が繁殖することです。
この問題を解決するため、原則として抜歯を行います。
ただし、炎症が起きていると麻酔が効きにくいため治療を進められません。
したがって、まずは局所洗浄後に抗菌薬を投与して炎症を抑えます。
痛みが生じている場合は鎮痛剤も投与します。
ちなみに、治療により症状は軽減しますが、親知らずをそのままにしておくことはおすすめできません。
炎症の原因を取り除かないと、再発を繰り返す恐れがあるためです。
手順②歯肉を切る
斜めや横に生えた親知らずは、汚れが溜まりやすい状態です。
たとえば、歯肉が被っているとポケット(歯と歯肉の隙間)に汚れが溜まってしまいます。
放っておくと炎症の原因になるため、被っている歯肉を切除することがあります。
ただし、根本的な解決にはなりません。
炎症を繰り返す恐れがある場合は、原則として抜歯が必要です。
手順③炎症が治まったら抜歯する
抗菌薬を投与して、炎症が治まったら親知らずを抜歯します。
具体的な手順は、親知らずの生え方などで異なります。
参考に、歯肉に埋まっている親知らずの抜き方を紹介します。
【抜歯の流れ】
- レントゲン撮影、CTスキャンなどで歯、血管、神経の位置などを確認する
- 局所麻酔を行う
- 歯肉を切り開く
- 歯槽骨を取り除く
- 切削器を使って親知らずを切断する
- 歯冠部分を取り除く
- 歯根部分を取り除く
- 洗浄後に歯肉を縫合する
抜歯の方法や抜歯にかかる時間はケースにより異なります。
一定のリスクを伴うため、治療を受ける前に詳細を確認しておくことが大切です。
親知らずの治療費や期間の目安
親知らずの治療には、原則的に保険が適用されます。
抜歯から完治までの費用の目安は2,000~7,000円です。
骨を削るなどの処置をせずに抜歯できる場合は、手術代800円に薬代を加えて、合計2,000円程度に抑えられます。
親知らずが骨に埋まっており、骨を削る処置が必要な場合は、手術代1,500円と薬代で、合計3,000円程度が目安です。
ただし、親知らずの生え方によってはCT検査など、追加の処置が必要なことがあり、それによって治療費もまた増えていきます。
抜歯の処置時間は、おおよそ1時間が目安です。
治療後3日で腫れのピークを迎え、1週間ほどで収まるでしょう。
具体的な治療の内容や費用、抜歯のスケジュールは歯科医師とご相談ください。
こちらの記事では、親知らずを抜く適切なタイミングについて解説していますので合わせてご覧ください。
関連記事:親知らずを抜くタイミングはいつがベストなのか?
親知らずの治療後にやってはいけないこと
親知らずを抜いたあとの傷口は、深い穴状になっており、傷が塞がるまでは丁重に扱わなければなりません。
この項では、親知らずの治療後にやってはいけないことを解説します。
歯を抜いた部分を指で触る
処置後の傷口はデリケートで、細菌に感染しやすい状態です。
抜歯後の傷を指で触れると、雑菌が繁殖し、強い腫れや開口障害を引き起こします。
重篤化した場合、抗生物質の投与など、別途で治療が必要になるおそれもあります。
傷が塞がるまでの傷口は、極力刺激を与えずに、衛生的に扱いましょう。
強くうがいをする
抜歯後の傷口には、血餅(けっぺい)というかさぶたのような血の塊ができます。
血餅には傷を塞ぎ、治癒を促進させる効果があります。
しかし、強くうがいをすると取れてしまうことがあるため、注意が必要です。
血餅が外れると、傷の治りが遅くなるだけでなく、激しい出血や痛みを引き起こしかねません。
抜歯当日は強めのうがいを避け、優しく口をゆすぐ程度に抑えましょう。
刺激物・硬いものを食べる
処置後は食べ物にも注意が必要です。
辛みの強い食品は傷口を刺激し、激しい痛みにつながります。
患部の炎症を悪化させるおそれもあるので、しばらくは控えましょう。
また、硬い食べものは血餅を欠落させ、患部を傷つける可能性があります。
抜歯後は刺激が少なく、柔らかい食品を食べるようにしてください。
シチューや雑炊、ヨーグルトなどがおすすめです。
喫煙する
タバコは傷の治りを遅くするので、抜歯後の喫煙は控えましょう。
タバコのニコチンには血管を収縮させる作用があり、傷の治癒に必要な血流を妨げます。
また、タバコに含まれる有害物質は人間の免疫力を低下させるので、傷口から感染症が発症するリスクを高めます。
それだけでなく、抜歯後に処方される痛み止めや化膿止めの効果を弱める作用もあり、傷の治りにおいて多くの弊害があるので、喫煙は控えたいところです。
長時間入浴をする
長時間の入浴は、全身の血行をよくするため、傷口からの出血を促してしまいます。
皮膚の傷と異なり、口内の傷にはかさぶたができず、通常以上に止血が困難です。
抜歯後3日間は、長時間の入浴を避けて、軽めのシャワー程度にとどめましょう。
関連記事:親知らずの抜歯後の痛みはいつまで続く?対処法も解説
親知らずは放置せず、適切に対処しよう
今回は、親知らずを放置した場合のリスクについて解説しました。
親知らずは不規則に生えてくることが多く、放置すると虫歯や歯周病を引き起こし、ほかの歯に悪影響を及ぼす場合があります。
親知らずが生えてきたら、「痛くないから」「少し出てるだけだから」と放置せず、歯科医師に相談しましょう。
コラム監修者
資格
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得