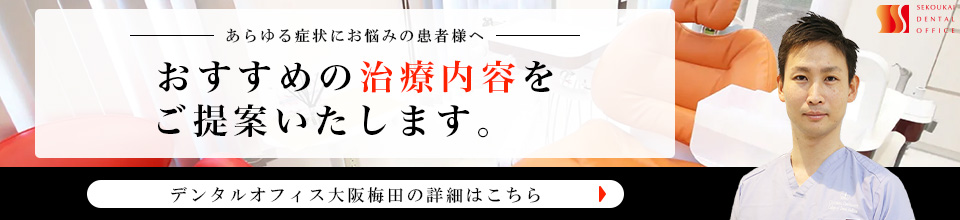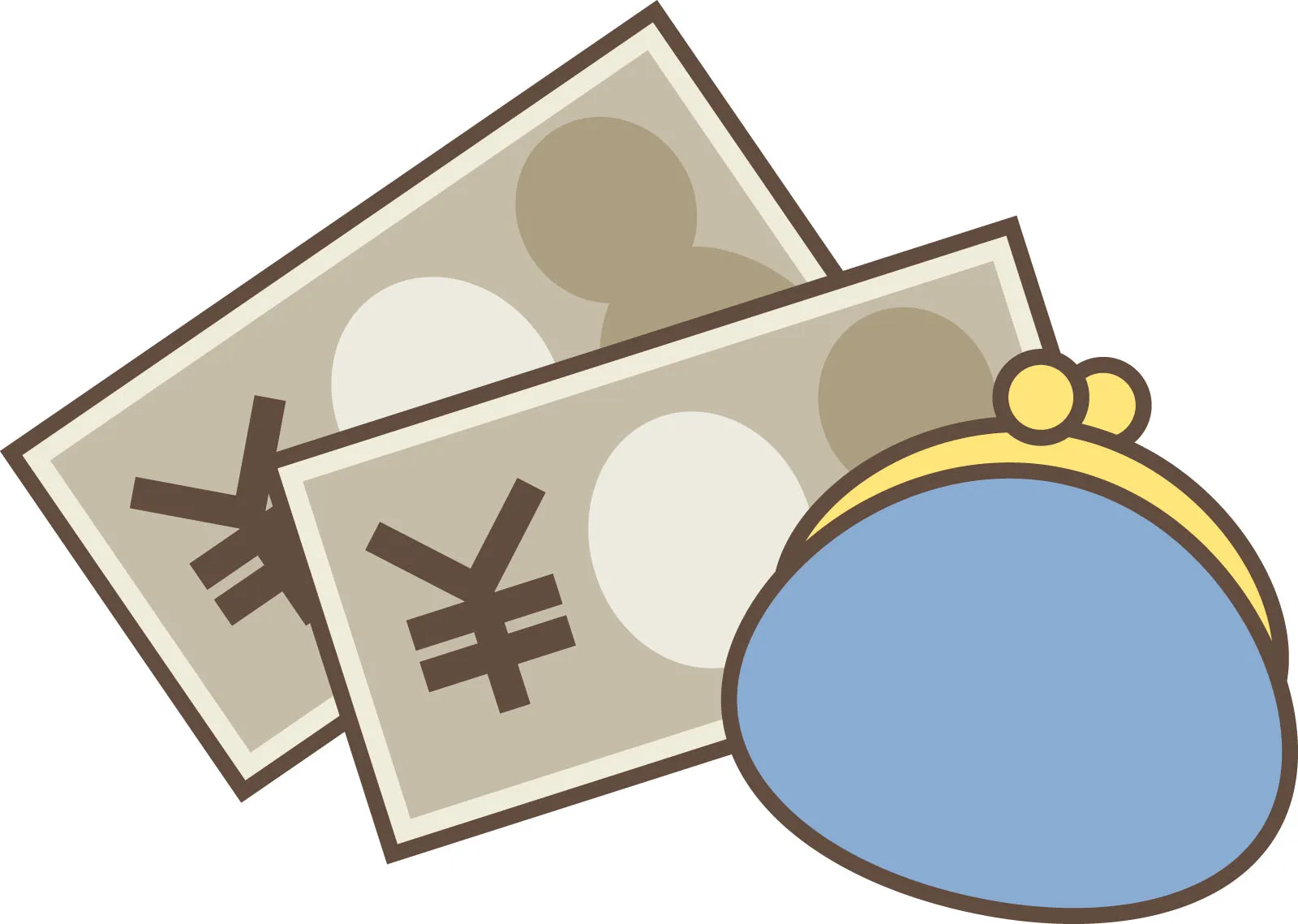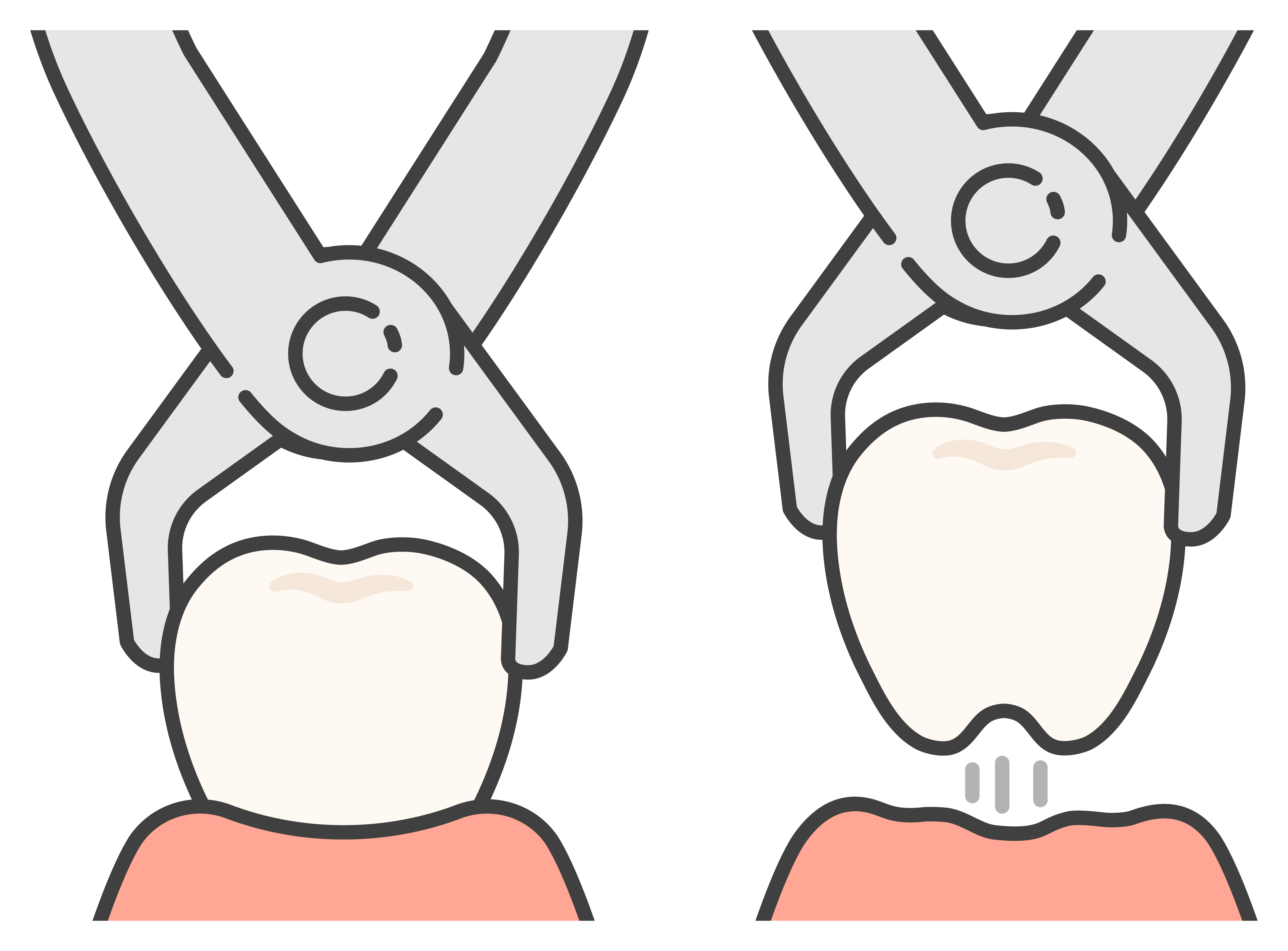梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」
〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画
歯周病は自然に治る?自宅でのセルフケアと歯科医院での治し方

歯周病を放置すると歯茎が炎症し、初期・中等度・重症へと進行します。
重症化すると骨まで溶けはじめ、歯が抜け落ちることもあります。
歯周病の治療は自力では行えないため、歯や歯茎に異常を感じたら早めに歯科クリニックへ相談しましょう。
この記事では歯周病の症状の進行度やクリニックでの治療方法、日頃からできるセルフケアについて詳しく紹介します。
口内ケアに悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください
目次
歯周病は治るのか?
歯周病は、口の中に棲みついている歯周病菌の感染によって引き起こされる炎症性の疾患です。はじめは歯肉炎と呼ばれる炎症の症状をきたし、そこから徐々に歯肉の中へと細菌が入り込んで、歯を支える骨までも溶かしてしまいます。
歯周病は、細菌が感染して炎症が起きている状態です。口の中にエサがあるかぎり細菌は活発に繁殖を続けるので、セルフケアによって常に口の中は清潔にしておく必要があります。
セルフケアだけでも症状の悪化は抑えられますが、自然に治るものではありません。歯肉炎という炎症の過程から歯周病に進行しているので、歯肉が赤く腫れあがる炎症よりもさらに重い状態になります。歯石や歯垢といった汚れを物理的に取り除かなければ、症状の改善が期待できないことに注意が必要です。
歯周病の治療を自宅で出来ない理由
歯周病の主な原因は、歯周病菌の塊である「歯石」であり、歯周病治療では歯石の除去を必ず行います。歯石の前段階である歯垢も、放置していると数日で石灰化して歯石になり、虫歯や歯周病の原因になります。
歯と歯茎をきれいに掃除するには、専門医の受診が必要になります。特に歯周病の治療は、どの程度進行しているのか、どのような治療が必要なのかを自分自身では把握できないため、歯科クリニックの受診が推奨されているのです。
口の中は複雑な形状をしており、自分で確認できない歯と歯の重なった部分や小さなすき間がたくさん存在しています。「歯周ポケット」と呼ばれる歯と歯茎のすき間も外からは目視できず、気づかないうちに汚れや細菌が溜まってしまうため、クリニックでの検査やクリーニングが必要になります。
こちらの記事では、歯周病治療の流れについて解説していますので合わせてご覧ください。
関連記事:歯周病治療の流れとセルフケアのポイントを紹介
歯周病の進行度
歯周病の症状は、主に初期・中等度・重症の三段階に分けられます。
進行度は、歯と歯茎の間の隙間である「歯周ポケット」の深さによって判断します。
- 初期:2~5mm
- 中等度:5~7mm
- 重症:7mm以上
一般的に歯周ポケットの深さが2mm未満であれば健康な状態であり、2mm以上になると初期症状とされます。
初期症状ではほとんど痛みを感じませんが、歯茎の色が薄ピンクから赤色へと変化します。
5mmから7mmの場合は中等度とされ、歯茎の腫れや出血が見られます。
また歯茎の下にある骨「歯槽骨」が溶けはじめ、歯がぐらついて違和感を感じたり、硬いものを食べにくくなったりします。
7mm以上になると、歯槽骨が3分の2以上溶けており、重症と判断されます。
歯茎の出血や痛みを頻繁に感じ、患部が化膿するためひどい臭いの口臭が発生します。
また歯を支える骨がほとんど溶けてしまっているため、歯が自然と抜け落ちることもあります。
歯周病が重症化すると外科手術が必要になる場合もあり、早期の治療が重要です。
歯科医院での歯周病の治療方法
歯科医院で歯周病を治療する場合、歯垢と歯石の除去が基本です。それ以外にも、歯周病の症状が軽度・中等度・重症と段階に応じたケアが行われます。それぞれの治療についてみていきましょう。
歯垢と歯石の除去
歯と歯の間に付着することが多い歯垢と、硬くこびりついて自力では取れなくなってしまう歯石はどちらも歯周病の原因になるため、定期的に清掃する必要があります。
柔らかい歯垢は自分でも除去できますが、クリニックでは歯の1本1本にフロスを使うほか、風や水をかけて洗い流し、器具を使って細かく取り除きます。
歯周ポケットができておりその中も汚れている場合は、ポケットの内部もきれいに清掃します。
軽症の場合
軽症の歯周病は歯肉が軽く腫れ、ピンク色から濃い色に変色するなど視覚的にも症状が出ている状態です。触ると出血する部分がある、歯には歯石がついているといったポイントも歯周病を判断する目安になります。
軽症であれば改善できる余地は十分にあり、歯垢・歯石の除去とブラッシングの徹底を心掛け、患者さん自身でもセルフケアをしっかりと続けるように指導されます。軽症であるほど治りが早く、元のすっきりとした健康な歯肉に戻ります。
中等度の場合
中等度の歯周病は、歯周ポケットが通常よりも深くなっています。歯石もついており、虫歯がみられるなど複合的な症状を抱える患者さんもみられます。
歯周ポケットが深くなっていると、歯肉で隠れている部分にもプラークが入り込みやすくなります。歯石をきれいに取り除くと同時にプラーク・コントロールも行わなければなりません。
歯周病菌を除菌する飲み薬の服用、舌や頬の粘膜のクリーニング、歯科用レーザーによる治療(レーザーディプライトメント)で改善を行います。クリニックにより対応可能な治療が異なるため、事前に確認のうえ受診してください。
重症の場合
歯周病が進行すると、歯周病菌が歯槽骨を溶かしていきます。
この段階では歯槽骨に大きな穴が開いており、そこから歯石や細菌が入り込むことがあります。
歯茎の深い部分に歯石や細菌が溜まると、周囲の歯周組織まで失われてしまいます。
このような状態になると、通常の歯科治療では対処が難しく、外科的治療が必要となります。
歯周組織の治療には、再生医療を活用して患部の回復を図ります。
重症化した歯周病では、歯槽骨がほとんど失われ、歯がぐらついて不安定になります。
一度溶けた骨は再生しないため、このような不安定な歯を治療するには抜歯が必要となります。
ぐらついた歯を放置しておくと周囲の健康な歯にも負担をかける可能性があるため、医師に相談し、早めの治療を受けましょう。
歯周病で行われる外科治療
歯周病は重症の場合、外科治療が必要になることがあります。
ここでは歯周病の外科治療について詳しく説明します。
歯周外科手術
歯周病は悪化すると、歯石が歯茎の奥にまで付いてしまいます。
歯石は細菌繁殖の温床となるため、歯茎を切開して、歯茎の奥にある歯石を除去します。
歯茎が下がり歯周ポケットが深くなった場合は、歯肉を切開して歯槽骨の形を整える「切除手術」が行われ、歯石が溜まりにくい状態にします。
歯周組織再生療法
歯周病によって歯茎や歯槽骨が損傷した場合は、再生療法による治療が行なわれます。
歯茎の場合は健康な部分の歯茎を切り取って患部に移植し、歯茎の再生を促します。
歯槽骨が溶けている場合は、特殊な人工膜を用いる「GTR法」や、タンパク質の一種を歯根面に塗布して再生を促す「エムドゲイン法」が行われます。
症状によって適した治療法は異なるため、歯科医と十分に相談し、自分に合った再生療法を選ぶことが大切です。
歯周病の治療を受ける際に押さえておきたいリスク
歯周病の治療には、いくつかのリスクも伴います。
歯周病の治療では歯周ポケットの歯石を除去しますが、その際に歯の根の部分(歯根)が露出し、知覚過敏などの症状が生じることがあります。
通常、歯はエナメル質と呼ばれる硬い組織に覆われていますが、歯根部にはエナメル質がなく、象牙質が露出しており、この部分はどうしても刺激に敏感になりやすいのです。
これは歯石除去によって象牙質が一時的に外気に触れるためであり、刺激に慣れるにつれて次第に知覚過敏は落ち着いていきます。
歯周病の治療に複数回通院が必要な理由
歯周病の治療は、治療の初期段階から少しずつ変化をみて進めていきます。
歯茎が歯周病にかかってしまった場合、1回の治療で完治することはありません。外科的手術や自費診療を行う場合でも、基本的に複数回の通院が必要です。
歯周病のセルフケアの方法
歯周病にかからないために、また初期の段階で進行を抑えるには、セルフケアが大切です。ここからは、歯周病を予防するために意識したいセルフケアについてチェックしていきましょう。
歯周ポケットを意識したブラッシング
歯周病の原因となる歯石はブラシをきちんと当てなければ取ることはできません。
実際、普通の歯磨きでは全体の50%程度しか汚れが取れていないと報告されています。
特に歯周ポケットの歯の間や根本は小さく、狭いため、ブラッシングが難しい部位です。
次のポイントを参考に、歯周ポケットを意識してブラッシングを行いましょう。
ブラッシングのポイント
歯を丁寧に磨こうとすると力が入りやすいものの、ブラッシングに強い力は必要ありません。
軽く毛先を歯に当て、小刻みに振動させるように動かすのがポイントです。
また、歯ブラシは歯に対して45度から90度で当て、歯の根元を意識してブラッシングしましょう。
歯周ポケットや奥歯は通常の歯ブラシでは磨きにくいため、先端が小さいタフトブラシを併用すると、清掃効果の向上が期待できます。
通常の歯ブラシとタフトブラシを場所によって使い分けることで、歯周病を予防する効果が見込めます。
歯間ブラシやデンタルフロスの使用
歯垢を残さず、歯石を防ぐためには歯間ブラシやデンタルフロスを活用しましょう。歯と歯の間に入り込みやすく、使いやすいものを使用することが大切です。
ブラッシングだけでは細かな汚れが取り切れないため、食べものを咀嚼したあとはできれば歯間ブラシやデンタルフロスを使用しましょう。
殺菌効果のあるうがい薬
殺菌効果のあるうがい薬も、口の中に残っている細菌に対して有効です。成分にもよりますが、除菌効果があるものは歯周病菌や虫歯菌を除菌する機能があり、歯ブラシがかけられない喉のほうまでカバーできます。
歯間ブラシやデンタルフロスのほかに、うがい薬も使いやすいものを選んでみてください。
関連記事:歯周病の症状・原因と今日から取り組める4つの予防法
歯周病の初期症状
歯周病の治療は、早期に行うことが大切です。
ここでは早めに歯周病に対処できるように、歯周病の初期症状についてお教えします。
- 歯茎が赤く腫れ、かゆみを感じる
- 歯磨きをすると歯茎から出血する
- 冷たいものを飲むとしみるように痛む
- 口臭の悪化
- 歯茎が下がる
歯周病は世界で最も患者が多い感染症とされ、歯周病になっていても無自覚な人は珍しくありません。
紹介した内容を参考にし、異常を感じたら早めに歯科クリニックを受診しましょう。
歯周病の専門的なケアはクリニックへ
ここでは歯周病の特徴と治し方について紹介しました。
歯周病の予防には日頃のセルフケアが欠かせませんが、症状が進行した場合には専門的な治療が求められます。
また、歯周病は自覚しづらい病気でもあるため、定期的に歯科医院で歯石除去をしてもらい、歯周病の検査もすると早期発見につながります。
大阪梅田のインプラント治療なら「デンタルオフィス大阪梅田」
コラム監修者
資格
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学