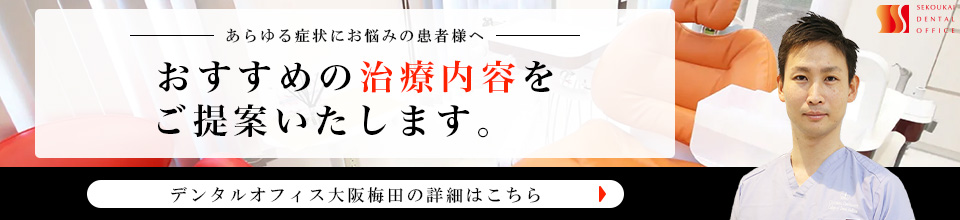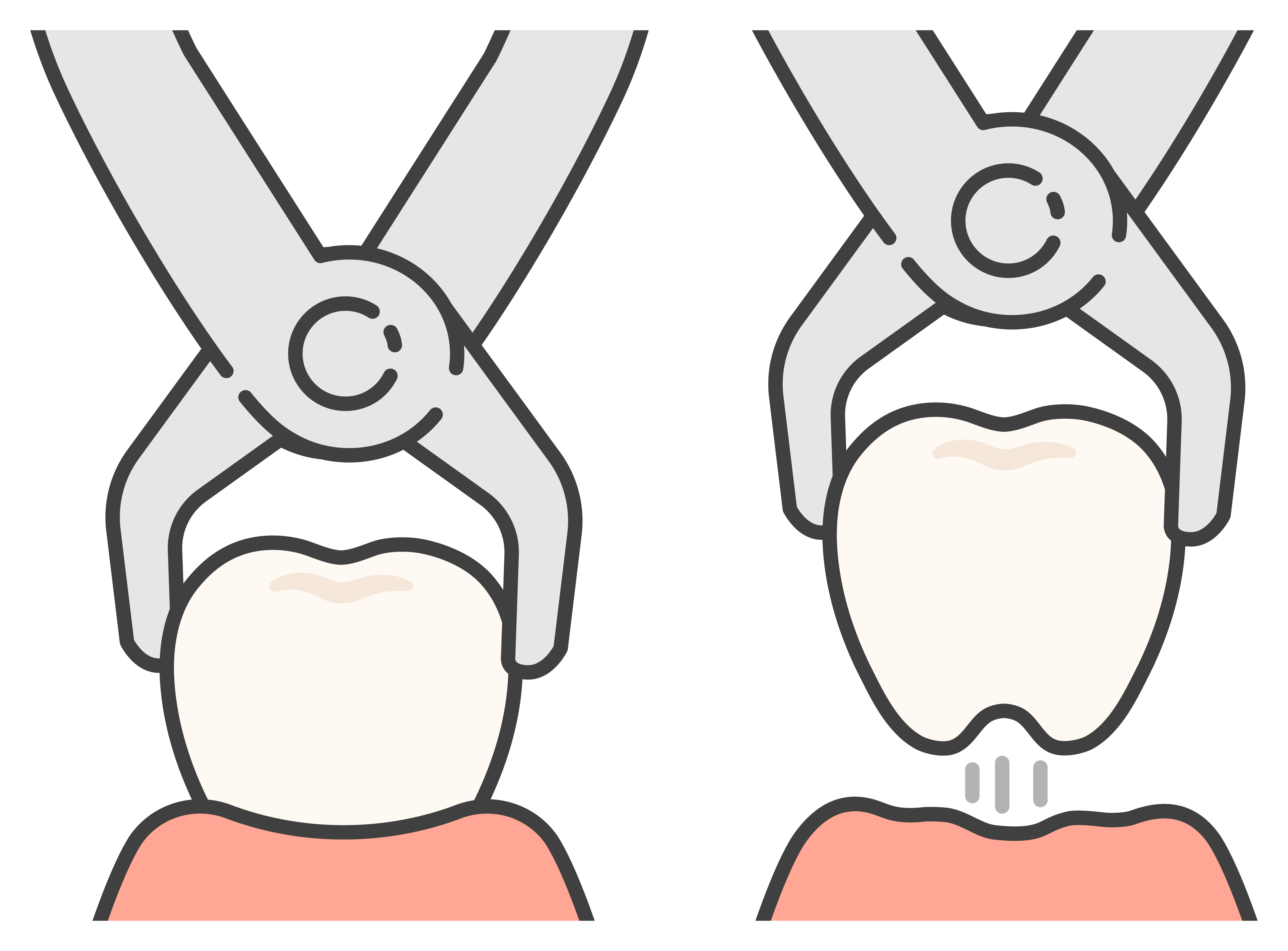梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」
〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画
歯周病の症状・原因と今日から取り組める4つの予防法

「歯磨きをすると歯茎から血が出る」「これって歯周病の症状?」などの疑問を抱いていませんか。
歯を失う2大原因のひとつと聞くと、不安になってしまいますよね。
歯周病になると、歯茎から血が出るなどさまざまな症状が現れます。
気になる点がある方は注意が必要かもしれません。
ここでは、歯周病の原因と症状を解説するとともに歯周病の予防方法を紹介しています。
何かしらの症状が現れている方などは参考にしてください。
梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください
目次
歯周病の原因
歯周病は、歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)から侵入した細菌が歯肉で炎症を起こしたり歯槽骨を溶かしたりする病気です。
以上からわかる通り、細菌(歯周病原菌)が深く関わっています。
ポイントは、A.a.菌、P.g.菌、P.i.菌、T.f.菌、T.d.菌など、複数の歯周病原菌が関わっていることといえるでしょう。
歯周病の直接的な原因は、これらの細菌が歯周ポケットで繁殖することです。
具体的には、細菌が産生した毒素により炎症が引きこされます。
歯周病になると、どのような症状が現れるのでしょうか。
歯周病になると現れる症状
歯周病の主な症状は次の通りです。
【主な症状】
- 歯がぐらつく
- 歯茎が腫れている
- 歯茎が痩せてきた
- 歯茎から出血する
- 歯茎から膿が出る
- 口臭が強くなる
- 冷たいものがしみる
- 歯茎下がりが気になる
歯周病になると、歯茎が赤くなる、ブラッシングで出血する、歯と歯の間の歯茎が腫れるなどの症状が現れます。
さらに進行すると、歯茎が赤紫色になる、ブラッシングで血や膿が出る、歯茎が痩せて歯が長く見える、歯がぐらぐらするなどの症状が現れます。
初期の段階では自覚できる症状を現しにくいため、セルフチェックや歯科クリニックの健診を受けて早期発見に努めることが重要です。
こちらの記事では、歯周病と歯肉炎の違いについて解説していますので合わせてご覧ください。
関連記事:歯周病と歯肉炎の違い|押さえておきたいこれらの原因と対処法
歯周病の進行度とその症状
歯周病は進行するため、軽度のうちに治療を始めることが重要です。
歯周病の進行度とそれぞれの症状について解説します。
第一段階
歯周病の第一段階は「歯肉炎」です。
歯と歯の間や歯と歯肉の間にプラークが溜まると、歯肉に炎症が起こります。
歯肉が充血して赤くなる、歯磨きのあとに出血が見られるなどの症状がある場合は、歯肉炎が起きていると考えられるでしょう。
第一段階で治療を始めれば、丁寧なブラッシングと定期的なクリーニングで症状を改善できます。
第二段階
歯肉炎の症状が進行すると「軽度歯周炎」となります。
歯肉の炎症だけでなく、歯槽骨が溶け始め、歯と歯茎の間に隙間ができることもあります。
歯茎が下がって歯が長く見える、口臭が強くなる、歯茎から血や膿が出るなどの症状を訴える方もいます。
歯茎の切開や歯石除去など、継続的な治療が必要になります。
第三段階
歯周病の第三段階は「中程度歯周炎」です。
歯茎からの出血がひどくなり、口臭がさらにきつくなります。
歯がぐらつく、しっかり物を噛めず食べにくいなどの症状が出て、初めて中程度歯周炎に気づく方もいます。
歯茎の色が赤黒くなってきた場合は注意が必要です。
第四段階
歯周病の最終段階は、重度の歯周炎または歯槽膿漏です。
歯茎が大幅に下がって歯がぐらつく、食べ物を噛むと痛みを感じる、口臭が非常にきつくなるなどの症状が出ます。
歯を支えている骨が破壊されるため、歯が抜けることも珍しくありません。
重度の歯周病になると、歯周病原菌が血液を通じて全身に回り、心血管疾患や糖尿病、がんなどのリスクを高めるおそれがあるため、早めの治療が大切です。
歯周病によって歯を失うリスクは?
歯周病が進行すると、健康な歯を失うことになりかねません。
歯を失うとどのようなリスクがあるか解説します。
リスク①歯並びが悪くなる
歯周病により歯を失うと、歯並びが悪くなります。
歯を失うと、その隙間を埋めようとして隣接する歯が動きます。
他の歯も連鎖的に動いていくため、歯並びやかみ合わせが悪くなるのです。
リスク②口元に自信を持てなくなる
歯周病が進行して歯が抜けると、口元の見た目が悪くなり、自信を失う原因になることがあります。
とくに笑ったときに他の人から見える部分の歯を失うと、笑顔を作るのが嫌になると感じる方は少なくありません。
人と話す際も、口元を見られているのではないか気になってしまいストレスになることもあるでしょう。
歯周病が進行すると口臭がきつくなるため、誰とも話したくないと感じる方もいます。
リスク③顔の印象が変わる
歯が抜けることで、顔のバランスや形が変わってしまうケースもあります。
通常、食べ物を噛むことで顎骨に刺激が伝わり顔の形が維持されています。
歯を失うと、その部分に刺激が伝わらず、顎の骨が痩せてしまうことがあります。
骨の減少に伴い、歯茎に届く栄養が減り歯茎も下がっていきます。
顔の印象が変わったり、左右のバランスが悪くなったりするなどの悪影響が出ることもあります。
リスク④食べられるものが減る
歯周病によって歯が抜けると、固いものを食べるのが難しくなります。
固いものを食べることで顎が鍛えられるため、顎の骨が徐々に減少していく恐れもあるでしょう。
食べたいものを避け、食べやすいものを選ぶようになると、栄養バランスが偏るおそれもあります。
リスク⑤発音がしにくくなる
歯を失うと発音がしにくくなり、言葉を発する際にも不便を感じます。
歯が抜けた部分に空気が通るようになり、これまで通り発音するのが難しくなるでしょう。
自分の言ったことが聞き取られにくくなるため、コミュニケーションを取るのが嫌になる恐れもあります。
歯周病がもたらす身体への影響
歯周病は、口内だけではなく全身に悪影響を及ぼします。
歯周病の原因となる細菌が血液を通じて全身に回ることで、さまざまな疾患のリスクが高まります。
たとえば、歯周病原菌はインスリンの分泌を阻害するため、糖尿病を引き起こすことになりかねません。
歯周病原菌は動脈硬化を促進し、心臓疾患や脳疾患に罹る危険性もあります。
妊娠中の方は、歯周病によって早産や低体重出産のリスクが高まることが知られているため、早めの治療が大切です。
歯周病になりやすい人の特徴
歯周病は誰にでも起こり得る病気ですが、なりやすい人にはいくつかの特徴があります。
たとえば、糖尿病を患っている方は免疫力が低下していることに加え、歯周組織の回復が遅くなり歯周病に対抗することが難しくなります。
喫煙している方、口呼吸している方も口内環境が悪化する傾向があるため要注意です。
ホルモンバランスの乱れや強いストレス、疲労などで免疫力が低下している方も、歯周病のリスクが高い状態といえます。
歯周病を予防する方法
歯周病の予防方法は次の通りです。
ポイント①口の中を清潔に保つ
基本の対策は、口の中を清潔に保つことです。
歯周病の直接的な原因は細菌の増殖であるため、口の中を清潔に保てば遠ざけられると考えられます。
具体的な対策として、丁寧なブラッシングとデンタルフロス・歯間ブラシの併用があげられます。
ブラッシングのポイントは次の通りです。
【ブラッシングのポイント】
- 歯と歯茎の境目に45度の角度で歯ブラシを当てる
- 力を入れずに左右に細かく歯ブラシを動かす
- 毛先を歯と歯茎の隙間に潜り込ませるように磨く
デンタルフロスは歯と歯が接している面を磨く補助器具、歯間ブラシは歯と歯の間にできた隙間を磨く補助器具です。
歯ブラシとは役割が異なるため、これらの補助器具も活用しましょう。
ポイント②よく噛んで食べる
よく噛んで食べることも歯周病予防につながります。
唾液の分泌を促せるからです。
唾液には、口腔内の細菌を洗い流したり殺菌したりする働きがあります。
口の中を清潔に保つ働きを備えているのです。
噛む回数が減って唾液の分泌量が減ると、口の中が汚れやすくなってしまいます。
噛む回数を増やすポイントは、適度な硬さの食材を食事に取り入れることです。
よく噛まなければ飲み込めないものがあると、意識しなくても噛む回数は増えます。
ただし、飲み込む力によってはのどに詰まってしまうことも考えられます。
食べる人の健康状態を考えて食材を選びましょう。
ポイント③十分な睡眠をとる
十分な睡眠をとることも歯周病の予防につながる可能性があります。
睡眠不足が続くと、免疫力が低下して歯周病菌が活性化してしまうからです。
また、自律神経のバランスが乱れて唾液の分泌量が少なくなることも考えられます。
これらを防ぐため、十分な睡眠をとることが大切なのです。
歯周病・糖尿病・睡眠の関係にも注意が必要です。
詳細は割愛しますが、睡眠不足になると糖尿病は悪化しやすくなります。
糖尿病になると歯周病は進行しやすくなります。
健康を守るため、睡眠不足が続かないように気を付けましょう。
ポイント④禁煙する
禁煙も歯周病を予防する重要な対策です。
タバコを吸うと、ニコチンの作用で血管が収縮するうえ白血球の機能も抑制されてしまいます。
腫れや出血が抑えられるため、歯周病を発見しにくくなる点も見逃せません。
喫煙は歯周病のリスクファクターです。
歯周病を予防したい場合は、禁煙を検討する必要があります。
ポイント⑤定期的にメンテナンスを受ける
歯周病を予防するため、歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることが非常に効果的です。
どれだけ丁寧にセルフケアをしても、プラークや歯石を完全に除去することはできません。
歯科医院で歯石除去やクリーニングを受けることで、歯茎の炎症を抑え、歯周病を初期段階で治療できます。
3か月に1回程度メンテナンスを行うことで、口腔内を清潔に保ち、虫歯や歯周病を早期に発見できるでしょう。
加えて、定期的なメンテナンスの際にブラッシング指導を受ければ、セルフケアの質をさらに高められます。
歯周病の症状に気づいたら歯科クリニックで相談
この記事では、歯周病の原因と症状、予防方法について解説しました。
歯周病は段階的に進行するため、初期のうちに治療を始めれば症状を抑えられます。
毎日の丁寧なブラッシングや睡眠に加え、定期的なメンテナンスを受けることで歯周病のリスクを減らせるでしょう。
よく噛んで食べる、禁煙に取り組むなど、生活習慣の改善を組み合わせることで、健康な歯を維持できます。
すでに何かしら歯周病の症状が現れている場合は、歯科クリニックで相談しましょう。
「デンタルオフィス大阪梅田」では、歯周病治療も行っています。
気になる点がある方は、お気軽にご相談ください。
大阪梅田のインプラント治療なら「デンタルオフィス大阪梅田」
コラム監修者
資格
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得