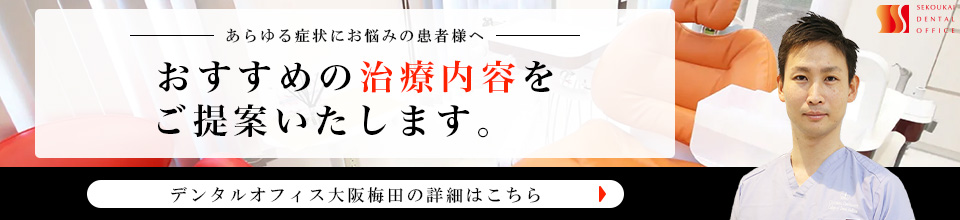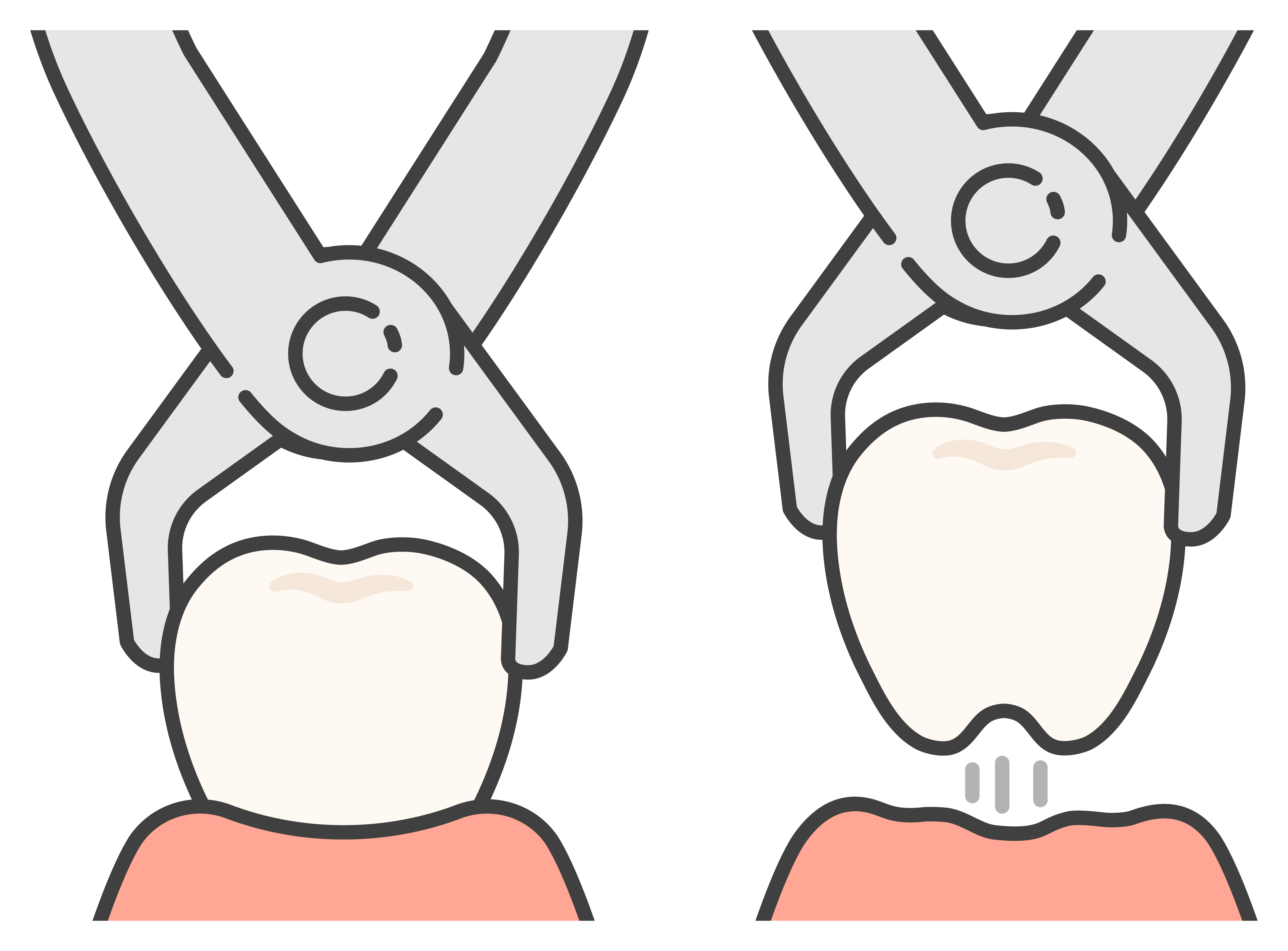梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」
〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画
親知らずが少し出ている場合の対処法と放置するリスク、抜歯後の注意点まとめ

親知らずが少し出ていると感じたら、どうするべきなのか気になるのではないでしょうか。
そのまま放置して問題はないのか、虫歯や歯周病の原因にならないか、さらに出てきたら困るのではないかといった不安は尽きません。
本記事では、親知らずが少し出ているとお感じの方に向けて、ケース別の対処法と放置した場合のリスク、そして親知らずを抜いた後の注意点などについて解説します。
必ずしも抜歯する必要があるとは限りませんが、親知らずのことが少しでも気になる方はぜひ参考にしてください。
梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください
目次
親知らずが少し出ているときはどうすればよい?
「親知らずが少し出ている」といっても、その状況はさまざまです。状況によって抜歯が必要なケースと、そうでないケースがあります。
最初に、抜歯が必要になる主なケースと、そうではないケースについて解説します。
抜歯が必要なケース
親知らずの抜歯が必要と考えられるケースは、主に次の5つです。
虫歯になりやすい場合
親知らずは一番奥に生える歯です。奥にある歯は歯磨き時にブラッシングが届きにくいため、親知らずを含めて奥歯は虫歯になりやすい特性があります。
そのため虫歯の治療をしてもまた虫歯になってしまうことも少なくありません。
何度も虫歯治療をするのは負担が大きくなりますし、根本的な原因が残ったままだと治療の回数がさらに増えてしまう可能性もあります。
この場合、根本的な原因である親知らずを抜いて汚れが溜まりにくい状態にすることが有効です。
横向きや斜めに生えている場合
他の歯と違って、親知らずは横向き、もしくは斜め向きに生えてくることがあります。
向きにかかわらず歯茎の中に埋まっているのであれば問題になりにくいのですが、親知らずが歯茎から出ている場合は汚れが溜まりやすくなり、またブラッシングも届きにくいスペースができてしまいます。
こうしたスペースは炎症や虫歯の原因となるため、対処が必要です。
横向きや斜め向きに親知らずが生えていて歯茎から少し出ている、さらにそのせいで腫れや痛みを感じているのであれば、根本的な原因である親知らずを抜く治療が推奨されます。
噛みあう歯が存在しない場合
歯は上顎と下顎の両方に生えており、上下の歯が噛み合うように並んでいます。
上下で噛みあう歯があることによって歯に汚れがつきにくくなるのですが、噛みあう相手となる歯がない場合は、汚れがつきやすく、そして溜まりやすくなります。
親知らずが少し出ていて、その反対側の顎に噛み合う相手となる歯がない場合は、そこに汚れが溜まりやすくなり、虫歯や歯周病などの原因になります。
さらに、噛みあう相手がいないと最初は少し出ているだけだった親知らずがさらに出てきてしまい、反対側の歯茎に当たって痛みを感じるようになる恐れもあります。
こうした問題は放置していると悪化するため、親知らずを抜くのが有効な治療法です。
口臭の原因になっている場合
親知らずの周りや歯の隙間などに汚れが溜まり、ブラッシングではなかなか汚れを取り除けない状態が続くと、虫歯や歯周病だけでなく口臭の原因にもなります。
虫歯になると歯に穴が開くため、そこにも口臭の原因となる細菌が溜まりやすくなってしまいます。
口臭は周囲に不快感を与えるだけでなく、口の中のさまざまな問題の引き金にもなりかねません。
この場合も、親知らずを抜くことで根本的な原因を取り除くことができます。
歯並びに影響を及ぼしている場合
親知らずが生えている向きによっては、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。
歯並びとの関係で注意したいのが、親知らずが手前に倒れた形で生えている場合です。
歯は根の部分から頭の部分に向けて動く性質があるため、手前に倒れた形で生えていると手前方向に力をかけてしまい、歯並びを悪くする恐れがあります。
これを放置していると歯並びが悪くなり、さらに虫歯などの原因を作ることにもつながるため、抜歯が有効な治療となります。
抜歯が必要ないケース
親知らずを抜くことを推奨されるのは、主に横や斜めを向いて生えていて、それが歯茎から出ている場合です。
その逆に親知らずがまっすぐ上に向けて生えていて噛みあわせに問題がないのであれば、今すぐ抜歯をしなくても問題はないでしょう。
もう一つ、親知らずが歯茎から出ておらず完全に埋まっているのであれば、これも抜歯の必要はないと考えられています。
また、親知らずは他の歯を抜いたところに移植できる可能性があります。
これを再植といいますが、親知らずの状態が再植に使えそうな場合も、あえて抜歯をせずに残すことがあります。
少し出てきた親知らずはどのように抜歯する?
完全に出ている親知らずであれば一般的な抜歯と同じ方法で抜くことができますが、少し出ている親知らずの場合は必要に応じて歯茎を切開し、親知らずを抜きやすくします。
切開や抜歯と聞くと痛みに不安を感じる方は多いかもしれませんが、局所麻酔をした上で行われるため、痛みを感じることはありません。
ただし、麻酔が切れてからは傷口が痛むことがありますが、痛み止めの処方を受けることによって痛みを感じる前に予防することもできるため、痛みについての不安はしっかりと歯科医師に相談するようにしましょう。
親知らずを抜く前に行う検査
親知らずを抜く前には、入念な検査が行われます。
人によって親知らずの生え方は異なるため、レントゲンや必要に応じてCTなどを用いて親親知らずの生え方の向きや神経・血管の位置関係などを確認します。
また、親知らずは生えている場所によっても検査のチェックポイントが異なります。
上顎に生えている場合はすぐ近くにある上顎洞という空洞との位置関係を入念にチェックし、下顎に生えている場合はすぐ近くにある下顎管という神経や血管が通っている部分との位置関係をチェックします。
少し出ている親知らずを放置するリスク
少し出ているだけだと思って親知らずを放置していると、思わぬ事態になることがあります。
ここでは、親知らずを放置することで考えられるリスクについて解説します。
リスク①虫歯や歯周病になる可能性がある
少し出ている親知らずは、汚れが溜まりやすいスペースを作る原因になります。
そのスペースには歯ブラシのブラッシングも届きにくいため、磨き残した汚れが虫歯や歯周病を引き起こす原因となります。
ひとたび虫歯になってしまうと一番奥にある歯だけに治療が難しく、治療をしても再び虫歯になるリスクも残ります。
リスク②隣接する歯に影響を及ぼす
前項と同じ理由で、親知らずは隣の歯にも影響を及ぼすことがあります。
というのも、少し出ているだけの親知らずは隣にある歯との間に溝を作ることになるため、その溝に汚れが溜まり、磨きにくい点が問題です。
親知らずが生えている向きによっては隣の歯に力を加えてしまうため、その状態が続くと全体の歯並びに影響を及ぼすこともあります。
リスク③痛みや腫れを引き起こす可能性がある
健康な時には気にならないかもしれませんが、疲れている時や体調が悪い時など体力が落ちると少し出ている親知らずのリスクが表面化して、痛みを感じたり腫れたりすることがあります。
炎症が起きても痛み止めや抗生物質で治療が可能ですが、根本的な原因は残ったままです。
一度炎症を起こすと再び炎症が生じやすいため、根本的な治療を受けることが望ましいです。
親知らずを抜いたあとの注意点
親知らずを抜いた後に、注意するべき点について5つの項目で解説します。
スムーズな回復と治癒のために、以下の項目をしっかり理解・留意しておきましょう。
注意点①傷口を触らないようにする
親知らずを抜いた後には、傷口が残ります。
抜歯をした直後は傷口が気になって舌や指で触って状態を確認したくなることがありますが、むやみに触ると出血や傷口が開いてしまう原因になります。
さらに、指から細菌に感染する恐れもあるため、親知らずを抜いた後は傷口を触らないようにしましょう。
注意点②頻繁なうがいは避ける
親知らずを抜いた場所には、傷口を覆うような形で血餅ができます。
この血餅は血の塊でできていて、傷口を守るためにできる体の自然な働きです。
血餅が傷口を守っている間に傷口が治っていくのが自然な治癒の流れですが、強いうがいや頻繁なうがいをすると血餅がはがれ、流れてしまいます。
血餅がはがれると傷口の治りが遅くなってしまうため、血餅がはがれるような強いうがいは控えましょう。
注意点③血行が良くなる行動を避ける
全身の血行がよくなるようなことをするのも、抜歯後は控えるべきです。
具体的には、激しい運動や熱いお風呂に長く浸かること、そして飲酒などです。
血行がよくなると出血や腫れ、痛みの原因となるため、痛み止めや腫れ止めの薬を処方されている場合は、その薬の効果を弱めることにもつながります。
注意点④喫煙を控える
喫煙をすると、タバコに含まれているニコチンが血管を収縮させ、血行を悪くします。
親知らずを抜いたことによる傷口を自然に治すためには患部に十分な酸素が行き渡ることが重要ですが、ニコチンがそれを妨げてしまいます。
痛みや腫れが長引く恐れもあるため、少なくとも傷口が治るまでは喫煙を控えることをおすすめします。
注意点⑤すぐに食事をとるのは避ける
親知らずを抜く際には、麻酔を使用します。
麻酔はおおむね数時間で効果が切れるので、それまでは食事を控えるようにしましょう。
麻酔が効いた状態で食事をすると熱さを感じられず口の中を火傷してしまう恐れがありますし、患部に血餅が作られる働きを妨げてしまうこともあります。
麻酔が切れて、食べ物の温度を感じられるようになってから食事をとるのが無難です。
また、麻酔が切れてからも、当初は柔らかい食べ物を選び、歯や歯茎への負担を抑えることが望ましいでしょう。
親知らずを抜く場合のクリニックの選び方
親知らずを抜くことを検討したら、次に重要になるのが歯科クリニック選びです。
歯科クリニック選びでは、以下の3つのポイントを意識するのがよいでしょう。
ポイント①感染症対策がしっかりしているかを確かめる
親知らずを抜く際には、歯科専用の医療器具を使用します。
この医療器具は複数の患者に使用するため、血液や唾液などを介した感染を防ぐための対策が不可欠です。
感染予防のための滅菌器には「N」「S」「B」のクラス分けがあり、このうち「B」が最も高いレベルの滅菌器です。
クラスBの滅菌器は器具の内部にまで水蒸気が行き渡って細菌を死滅させることができるため、衛生的です。
親知らずの治療をしに行ったのに細菌に感染して別の問題が起きてしまうことを防ぐためにも、感染症対策を徹底している歯科クリニックを選びましょう。
ポイント②リスクをきちんと説明してくれるところを選ぶ
親知らずを抜くのは外科的な治療なので、もちろんリスクもあります。
多くのメリットがある一方でリスクもあることをしっかりと説明してくれることは、歯科クリニック選びにおいて重要です。
抜歯後の生活における注意点まで説明してくれる歯科クリニックであれば、抜歯後のリスクを軽減できます。
ポイント③口腔外科も行っているところを選ぶ
口腔外科とは、口の中だけでなく顎や顔面など、口の周辺に関する治療を行う診療科目 のことです。
親知らずを抜く際には、上顎洞(上顎の中にある空洞)や下顎にある下歯槽神経などに関わる場合があります。
しかしながらこれらの部位は歯科ではなく口腔外科の領域になるため、歯科クリニックを選ぶ際には、口腔外科にも対応していることが重要なポイントです。
失敗しない親知らずの治療は、歯科クリニック選びから
親知らずが少し出ている状態を放置すると、さまざまなリスクにつながる場合が多いため、できるだけ早く歯科医師の診察を受けることが重要です。
しかも親知らずが生える方向や状態には個人差があります。
あらゆるケースに対応できる歯科クリニックを選び、抜歯後の注意点を理解した上で治療を受けることが望ましいでしょう。
大阪梅田のインプラント治療なら「デンタルオフィス大阪梅田」
コラム監修者
資格
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学